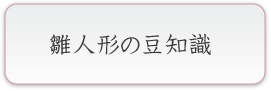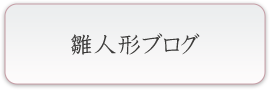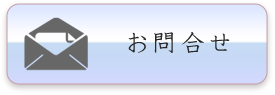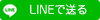1948年に祝日法が公布されたことによって、日本では正式に5月5日が「こどもの日」として国民の祝日になりました。この日は昔から男の子の成長をお祝いする「端午の節句」でもありましたが、現在では男女に関係なく世界的にも、全ての子どもたちのための日として決められています。
目次
端午の節句が男の子の日とされた理由
こどもの日の祝日が制定される前は3月3日は桃の節句で女の子の成長をお祝いする日、5月5日は端午の節句で男の子の成長をお祝いする日とされ、今でもその習慣は続いています。
端午の節句をはじめとする「節句」という行事は、1200年以上前から季節の変わり目に健康長寿を祈念する祭祀として、宮中貴族の間で行われていた五節句が起源です。
当時桃の節句や端午の節句は、子どものためではなく大人のための行事でした。

節句にはその季節に旬を迎える植物が使われ、端午の節句は、葉菖蒲の薬効成分を用いて祭祀を行なっていたことから別名「菖蒲(しょうぶ)の節句」とも言われました。
鎌倉時代になって武士が権力を持つようになると、尚武(武芸を尊ぶこと)と発音が同じことから、後継の男の子が生まれたことを神様や周囲に知らせるために吹流しや幟旗、武具を飾ってお祝いする形に変化したのです。
男の子の日というイメージが強くなったのは、この時代以降のことです。

「国立国会図書館デジタルコレクション」収録
(https://jpsearch.go.jp/item/dignl-1310782)
江戸時代になると、貴族や武家などの限られた人々だけで行われていた節句行事の習慣が一般庶民にまで広まりました。
商人たちが鯉のぼりや武者絵幟をはじめ、金太郎や桃太郎、鍾馗など、武士に限らず自由に飾ることができる五月人形を作り出したことで、端午の節句は全国的に男の子の成長と健康を祝う日として定着したのです。
端午の節句の意味

奈良時代に中国から伝わった暦の影響で、宮中貴族は奇数が重なる日を季節の変わり目と考えました。
体調を崩したり気分が落ち込むといった変調をきたす要注意日として、旬の植物の持つ力で邪気を祓い、ご馳走を食べて健康長寿を祈ったのが本来の節句行事です。
端午(たんご)の端という字は、端っこや際などを表す言葉として「最初」の意味があります。端午は5月最初の午(うま)の日のことで、それが毎年5日前後だったのです。
今では菖蒲の花も定番のアイテムとして五月人形に添えられますが、もともと節句に使われていたのは、清涼感のある香りで邪気を祓う効果があるとされるサトイモ科の葉菖蒲でした。
江戸時代の浮世絵にも葉菖蒲を軒下に吊るしたり、束ねて子どもたちが振り回したりする様子が描かれています。
それらの風習は時代の流れとともに薄れてしまいましたが、現代でも公衆浴場などで端午の節句に菖蒲湯を用意するところがあるようです。
こどもの日は何に感謝する日?

国民の祝日に関する法律を見ると、それぞれ、どういう趣旨で祝日になっているかが明記されています。例えば元旦は「年の初めを祝う」ための祝日と定められています。
何だか当たり前な気もしますが、では、5月5日こどもの日はどうでしょうか?
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」と書かれています。
こどもを大事に考える日であることは分かっていても、“母に感謝する日”でもあることは、意外とご存知ないのではないでしょうか?(実は私も知りませんでした)
これからは、こどもの日には家族みんなでご馳走を食べながら、お母さんに感謝の言葉を贈りましょう!
さいごに
時代の流れとともに、さまざまな変化を遂げてきた節句行事ですが、もともとは医療が発達していなかった時代に生み出された先人の知恵によるものです。
特に季節の変わり目に体調を崩さないよう、旬の植物や食べ物の力を取り入れる、といった考え方は、現代社会でも健康維持のために有効です。
また、子どもが元気で健やかに成長するということは、医学が発達した現代でも当たり前ではなく、
本人の努力や、家族のサポートがあってのことだと、いろいろな面で感謝する気持ちを持ちたいものです。