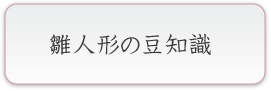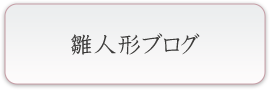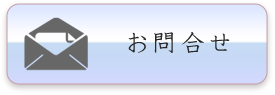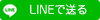五月人形の鎧兜飾りの後ろに立てる屏風と聞いて、すぐに思いつくのは「金屏風」だと思いますが、最近はいろいろなデザインの屏風が出回っていますので、金色とは限りません。
屏風のサイズも鎧兜の大きさに合わせて1メートルを超える物や30cm前後のコンパクトな物まで幅広く、飾り方も平飾りや高床式飾り、収納飾り、ケース飾りなど多岐に渡ります。
ケース飾りを除いて、それぞれのタイプに合わせて屏風も数多くのデザイン・サイズが作られています。よく見かけるのに意外と知られていない屏風について少し調べてみました。
目次
屏風は部屋の寸法に合わせてサイズが決まっていた


本来屏風は6枚からなる六曲屏風が基本の形とされ、曲げた1枚1枚のことを扇(せん)、屏風の数を数える単位は隻(せき)と言います。
また、2隻組み合わせて使うことが多かったことから、ペアでは双(そう)と言い、例えば「六曲一双」の場合、6枚からなる屏風が2つあるという意味になります。

魔除けとお守りの意味を持つ人形
「屏風」という言葉はもともと「風を防ぐ物」という意味です。屏風が日本に登場したのはかなり昔のことで、奈良時代には既に貴族たちの間で使われていたという記録があります。
昔の貴族の家は寝殿造という壁が無い建築様式で建てられていました。そのため屏風で部屋のように空間を区切る必要があったのです。
特に「身分の高い女性は公に姿を見せてはいけない」というしきたりもあったため、移動する際に屏風を目隠しに使っていたそうです。
部屋の間仕切りや風避け、目隠しとしても手軽に使えて簡単に片付けることができる屏風は、現代で例えると差し詰め便利グッズという感じでしょうか。
平安時代の貴族の恋愛模様を書いた「源氏物語」にも屏風や御簾といった物が度々登場しますが、風を遮るだけではなく裏で服を着替えたり身を隠したりと当時の生活には欠かせないインテリアのひとつだったようです。

その後、屏風にさまざまな絵が描かれるようになり、観賞用の目的も加わり、美術品としての価値も付加されるようになっていきました。
特に室町幕府の御用絵師だった狩野正信によって結成された狩野派や、尾形光琳、俵屋宗達といった日本画家たちによって、海外からも注目される美術品として確立されたのです。

屏風に似た使い方をする「衝立(ついたて)」と言われる物がありますが、曲げて自立する屏風とは違い、衝立には立てるための足がついています。
屏風はさまざまなイベントなどでも使われますが、特に印象深いのは結婚式や記者会見の金屏風ではないでしょうか。昔から屏風は高貴な人の背後に飾られることで特別感を演出する道具としても使われました。
光り輝く金色は魔除けの意味があり、邪気を祓う効果があるとされていたことも理由のひとつです。
雛人形のお内裏様の後ろにも金屏風が飾られていることが多いですが、これはもともと雛人形が高貴な人の婚礼の儀式を模して作られているからです。

さいごに
金屏風はおめでたいというだけではなく実際に人の顔を明るく照らしてくれますので、生き生きとした表情に見える効果があります。
晴れの舞台に相応しい映え効果な訳です。
また、金色に限らず、後ろに屏風があることで背景がすっきりとして引き立てる効果があります。
写真スタジオなどでも背景を一定にするための紙や布を使いますが、被写体をより引き立てるための工夫です。五月人形の鎧兜飾りの後ろに屏風を置く理由のひとつでもあります。