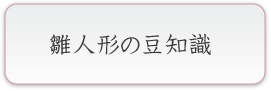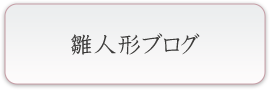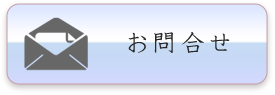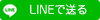雛人形に限らず人形を怖いと感じることがあるのはなぜなのでしょうか?
それは“人の形をした物には魂がこもる”といった昔からの言い伝えやホラー映画などの影響が大きいと考えられますが、雛人形などの節句人形は子どもが無事に成長するようにお守りとして飾る人形ですので怖いものではありません。むしろ身代わりとなって助けてくれるものなのです。
目次
雛人形の起源は平安時代の身代わり人形

医療が発達していなかった平安時代、子どもが無事に大きく育つことはとても重要なことでした。
そのため災いや病気などの悪いことが子どもに降りかからないように、身代わりとして人の形をした物を飾るようになったのが節句人形の起源だと言われています。
また3月3日は日本では桃の節句ですが、古来より中国では上巳(じょうし・じょうみ)の節句と言われ、穢れを川の水に流して清める日とされていました。
それがもともと日本で行われていた人の形をした紙や藁、木などを水に流して身を清める風習と結びつき“流し雛”という行事が生まれたと言われています。
これらのさまざまな習慣と平安貴族の子どもたちが小さな人形で遊んでいた“ひいな遊び”が融合し、雛人形やひな祭りへと変化していったのです。
人形には魂がこもる⁉︎

昔から“人の形をした物には魂がこもる”という言い伝えがあるのも、おそらく身代わりとして災難や邪悪なものを引き受けてもらう、という信仰に基づいているものと思われます。
昔ながらの雛人形の顔は妙にリアルな物も多いためまるで生きているように見えることも理由のひとつですが、これは江戸時代に節句人形が大流行し人形師がリアルな表情を追求した芸術性も関係しています。
また“人形が夜中に動き出す”といった迷信のような話や、“市松人形の髪が伸びる”など都市伝説や映画の影響からくるイメージもありますが、どれも真実ではありません。
一般的には災難や邪悪なもの=恐怖という考えにつながるため、人形=怖いという方向になったのかもしれませんが代わりに悪いものを引き受けて守ってくれる“お守り”だと思えば怖いというより有難い存在ではないでしょうか。
子どもの無事な成長を見守ってくれる

天皇家の婚礼の儀式を模した雛人形は、いつの時代も女の子の憧れです。
昭和初期くらいまでは雛人形は嫁入り道具のひとつで女の子が生まれると、その子のために新しい雛人形を買い足すというのが一般的だったようです。
子どもが無事に成長しずっと健康で幸せになってほしいと願う親心は、医療が発達した現代でも変わりません。そのために雛人形や五月人形などの節句人形が作られ続け初節句をお祝いする習慣も昔からずっと続いています。毎年雛人形を飾ることを楽しめるのは災いが無い証拠です。幸せなことではないでしょうか。
オススメの雛人形はこちら
雛人形は大きく分けて衣装を着付けた衣装着雛人形と木の筋目に布を挟み込んで作る木目込み雛人形の2種類に分かれますが、全体的に丸みをおびたフォルムが特徴的な木目込み雛人形は優しい雰囲気で人気を集めています。
また衣装が美しく見応えのある衣装着雛人形も近年は目がパッチリした温和な表情のものが人気です。
ここでオススメの雛人形をいくつかご紹介します。

宮びやかシリーズ 小三五親王 金彩 刺繍雛 二曲一双屏風 横幅60cm 商品番号:n23mb-c1
https://www.hinamatsuri-kodomonohi.com/view/item/000000003962
男雛、女雛ともに美しい桜柄の高級な衣装を着けた雛人形は、まさに日本の伝統的な芸術品です。お顔は現代風の温かみが感じられる表情でお部屋のインテリアとしても違和感なく飾ることができます。


マール 親王飾り 溜塗り四曲屏風 ティピシリーズ 横幅40cm 商品番号:mrl-c14
https://www.hinamatsuri-kodomonohi.com/view/item/000000004010?category_page_id=marle
工房天祥のマールシリーズは、コロンとした丸さが可愛らしい木目込み雛人形です。
木目込みタイプには珍しい入り目ですが、ふくよかなお顔でタレ目なのでまるで赤ちゃんのような優しい表情が魅力です。男雛・女雛だけの親王飾りから三人官女が加わった五人飾り、五人囃子まで揃った三段飾りまで種類も豊富です。

ウララ 親王飾り 和紙二曲屏風 ティピシリーズ 横幅30cm 商品番号:urr4
https://www.hinamatsuri-kodomonohi.com/view/item/000000003708?category_page_id=hina-bland-urara
こちらも工房天祥オリジナルのウララシリーズです。現代風にアレンジしたモダンでスタイリッシュな木目込み雛人形で、こちらも木目込み雛人形には珍しい入り目です。マールよりは少し大人っぽい表情ですが、可愛らしい子どものようなお顔立ちが印象的です。